
総合診療科インタビュー
INTERVIEW
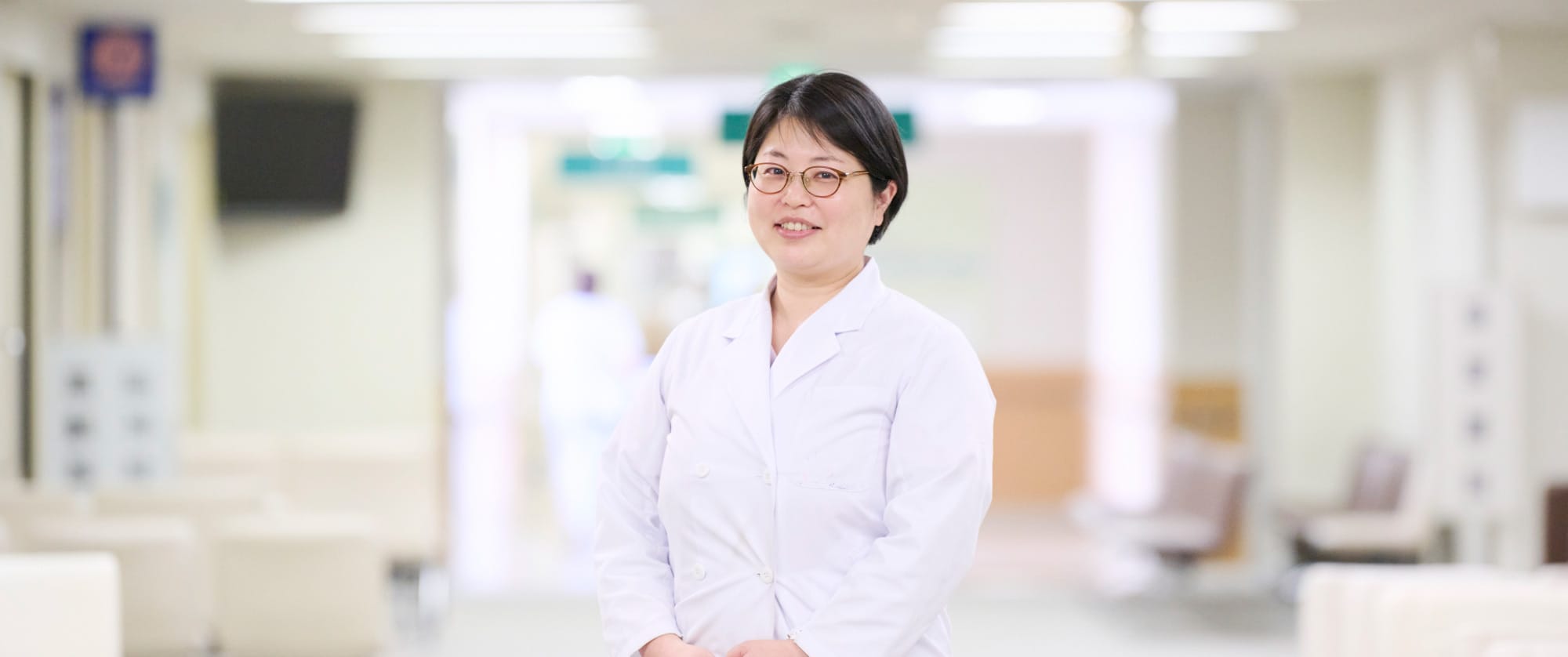
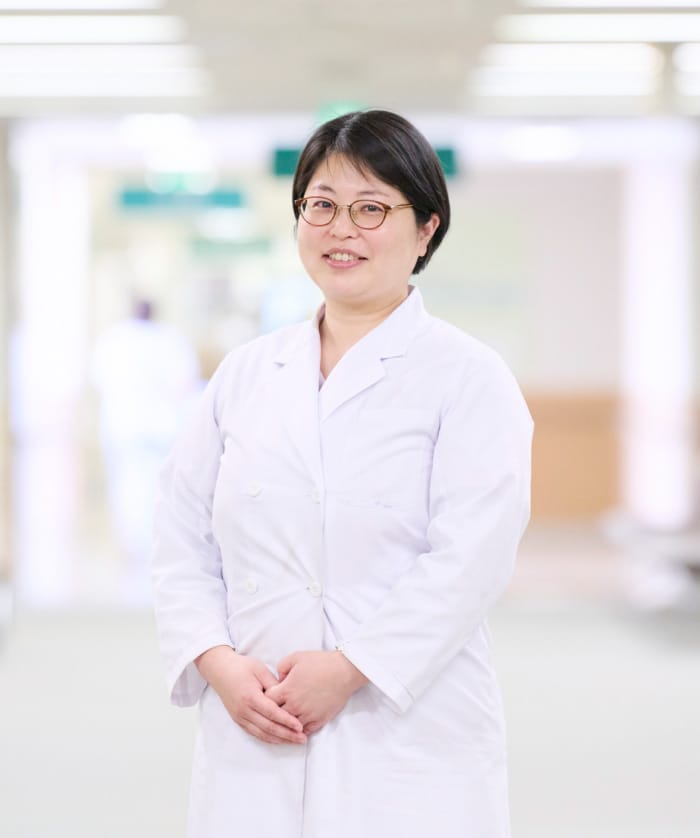
総合診療科 診療科長
山口 佳子
[専門領域] 総合診療
縦割りの患者情報を統合し、
原因の分からない症状を
解決に導く
南多摩地域における総合診療の最後の砦として、当科では診断のついていない患者さんをできる限り受け入れています。地域の先生方と密に情報共有し、縦割りのまま分断されがちな患者情報を統合し、原因がわからない症状をひとつでも解決に導き、患者さんの健康と地域医療に貢献したいと考えています。

多くの不確定な病態を診てきた経験を活かし
「よく分からない症状」を解決する糸口を見つけます
多くの患者さんにとって総合診療科は耳慣れない診療科で、知名度が上がってきたのはここ最近のことです。しかし、総合診療科を開設した後、うまく機能しないまま閉鎖となった医療機関も少なくありません。そのような状況下、東京医科大学病院(新宿本院)の総合診療科は15年以上診療を継続する老舗の1つで、私はそこで10年超の経験を積んできました。さらに地域の中核病院や在宅医療、離島でも診療を重ね、当科に来て3年ほどになります。一次医療である地域の診療所から、高度医療を担う三次医療機関での経験が糧となり、不確定な病態を見ることに慣れている、これが当科の強みにもつながっていると感じています。
各病院・各診療科の患者情報を統合する役割を担います
総合診療に携わっていて強く感じるのは、患者さんの情報がバラバラになり、地域で集約されていないことです。例えば、ご高齢の患者さんの場合、複数の医療機関、あるいは当院においても複数の診療科に通院されており、それぞれ専門的な治療を受けているにもかかわらず、実は主治医がいないという人が少なくありません。
このとき問題となるのが、情報が縦割りのままで統合されていないことです。例えば、当院で肺に癌の可能性がある影があると分かった患者さんが、高齢であることを理由に侵襲的な(身体への負担の多い)検査や手術を希望されなかったため、今後は尿の出を良くするための薬を処方されている、通院中の近くの内科診療所で健康診断等を定期的に受診するよう言われていたのを、尿の薬も余っているので特に受診されずに放置し、5年後に全身状態が悪くなり、呼吸困難と動悸で当科へ紹介されるようなケースです。各病院、各診療科で情報が共有されていないのは地域医療における根深い問題であり、回避しなければなりません。
これらの情報を統合することも、当科で果たすべき役割の一つと考えています。医療情報を丁寧に集約し、患者さんの病状の改善に活かせるようにしています。
大事に至る前に病気の存在を拾い上げる、チェック機能を強化します
上記のような事態を避けるためには、大事に至る前に拾い上げるチェック機能が必要です。その1つが患者さんとの日常的な関わりだと思っています。複数の診療科にかかる患者さんは「これだけ診てもらっていれば大丈夫」と安心されがちで、健康診断を受けていないという方もいらっしゃいます。かかわる医師の誰か一人でも、「健康診断は受けて下さいね」と、声をかけてさえすれば、病気を早期発見できる可能性が高まります。このチェックのポイントはいくつもあるはずですが、現状ではそれをすり抜けて重大な病気に至る方が多く見られます。私たち医師の確認次第でその予防が可能になると心得て、一緒にチェック機能を密にしたいと考えていますし、これには患者さんと近しい立場にいらっしゃるかかりつけ医の先生方のご協力が不可欠だと思っています。血圧などの薬の処方で来られた患者さんにも定期的に、胸の音を聴く、お腹を触る、足をみるといった機会をつくって頂ければと思います。
診断にさまざまな検査や時間を要するときは、
地域の先生方が深入りされる前に引き継ぎます
ご存知の通り、専門的な治療や検査を要するときに高度医療機関にご紹介いただくのが今の地域医療のあり方です。ですので、困ったときは早めにご相談いただきたいと思っています。
紹介状を書かれるタイミングは先生方によって異なると思いますが、解決に時間がかかりそうな場合は、複数の検査を進める前に是非当科に一度ご相談いただければと思います。
患者さんの症状が快方へ向かったことが確認できた際は、治療の方向性を示してかかりつけの先生にお返しする、あるいは必要な場合は院内他科の専門医に迅速につなぐことを基本としています。
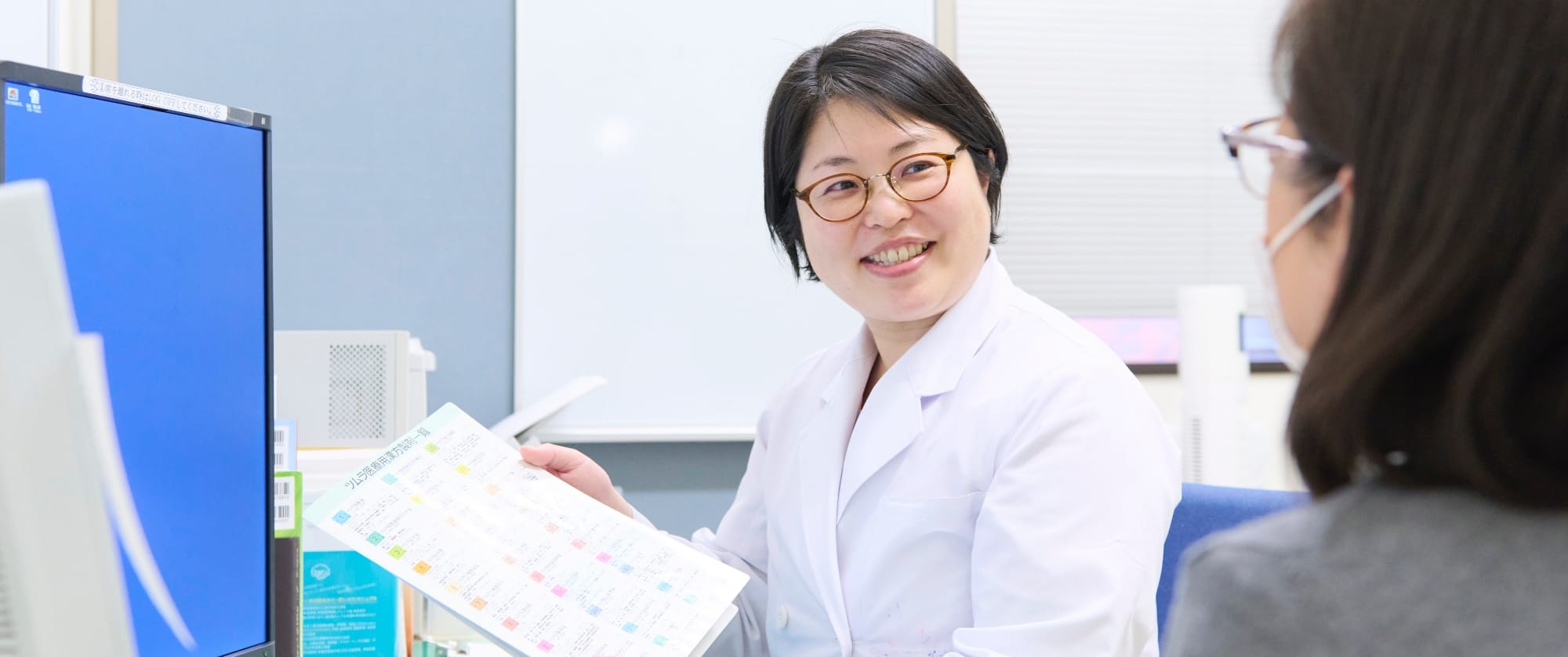
かかりつけ医の先生方にも患者さんのご意向を確認いただき
患者さんファースト医療を共に提供したい
原因がわからずにお困りの高齢の患者さんをご紹介いただくようなケースも多いのですが、ご紹介いただいた際には、すでに全身にがんが広がっている状態で、初対面で、その方の人生の最期に関することまでお話しをしないといけないことがあります。人間関係が築けていない状態で、初対面でそのようなお話をすることは、患者さんにとっても辛いことですし、よくよく話を伺うと、実は大学病院での検査や治療を望んでいない、かかりつけ医にずっと診て欲しかった、と漏らす方もいます。
在宅療養は可能か、面倒をみて下さるご家族はいるか、さらに検査を望むかなど、紹介前にかかりつけ医の先生方から患者さんのご意向をご確認頂くことで、患者さんファーストの医療が提供できると思っています。一方で、地域の先生方が患者さん一人ひとりの症状やご意向をつぶさに整理し問題解決するのは相当な労力と時間を要すると思います。そのために当科があるとは思っていますが、可能な範囲で事前に患者さんとご家族のご意向を確認いただくことで、患者さんにとって最適の選択肢を提示できる可能性が高まると思っています。
原因不明の発熱など、よくある例についても問題を共有し
一緒に診断への道筋をつけます
早めにご相談いただきたい典型例が、長く続く発熱です。高熱が続く場合や、血液検査で炎症の値が高いと抗生剤を処方されることが多いと思いますが、改善せずに別の医療機関にかかって同じ対応を繰り返される患者さんがいます。極端な例では、抗生剤を十数種類も使われて、紹介された方もいました。抗生剤の種類を変えても改善しなければ、細菌感染症以外の別の病気か、薬剤が原因であるなど、さまざまな原因が考えられますが、よく分からない病態を解決するのは難しいことです。しかし、患者さんは「現代医療なら調べれば分かるはず」と期待され、結果的に「原因が不明」と医師から聞かされると、“放り出された感”や不安が増大し、より症状が悪化することがあります。
発熱という一つの問題点でも、すぐに解決できないことは当科でもよくあります。しかし、「後医は名医」の言葉通り、時間の経過とともに所見が明確になり診断に結び付くこともあります。分からないなりに問題を一緒に共有・検討する。この繰り返しが解決への近道ではないでしょうか。当科では、ご紹介元の先生に丁寧にご返信し、患者さんの情報のキャッチボールをするよう心がけています。開業医の先生方とともにこのプロセスを継続し、地域全体の内科力、臨床能力を高める一助となれたらと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。
お問い合わせ
医療機関からのお問い合わせは、医療連携室で承っております。
受付時間をご確認の上お問い合わせください。
東京医科大学八王子医療センター
総合相談・支援センター医療連携室
TEL: 042-665-5611 (代表)
平日:9時~17時
第1・3・5週 土曜日:9時~13時
休診日:土曜日(第2・4週)、日曜日、祝日、4月の第3土曜日(大学創立記念日)、年末年始
患者様に関するご相談は、お電話でお問い合わせください。
ACCESSアクセス情報
〒193-0998 東京都八王子市館町1163番地
電車・バスでのアクセス
JR高尾駅/京王線高尾駅
高尾駅南口より京王バス3番乗り場(医療センター経由)館ケ丘団地行き「医療センター」下車
JR横浜線/八王子みなみ野駅
無料シャトルバス運行中
シャトルバス時刻表


